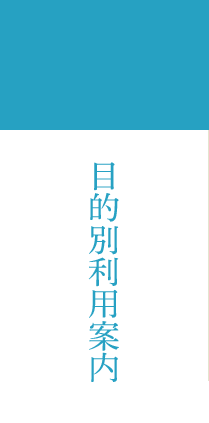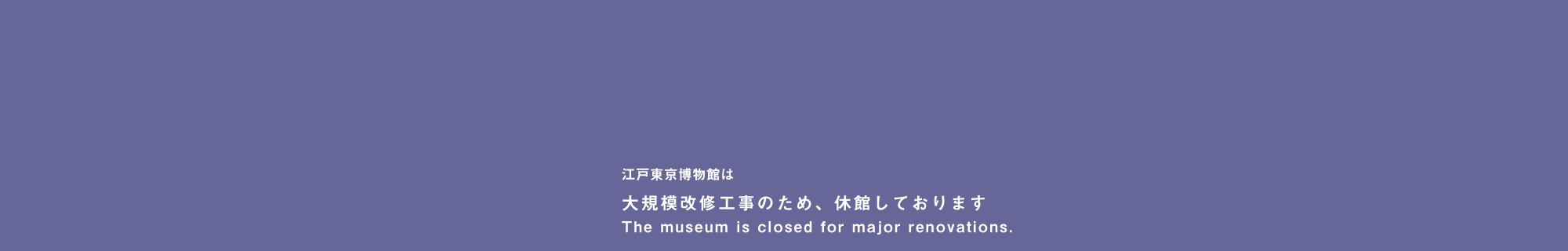
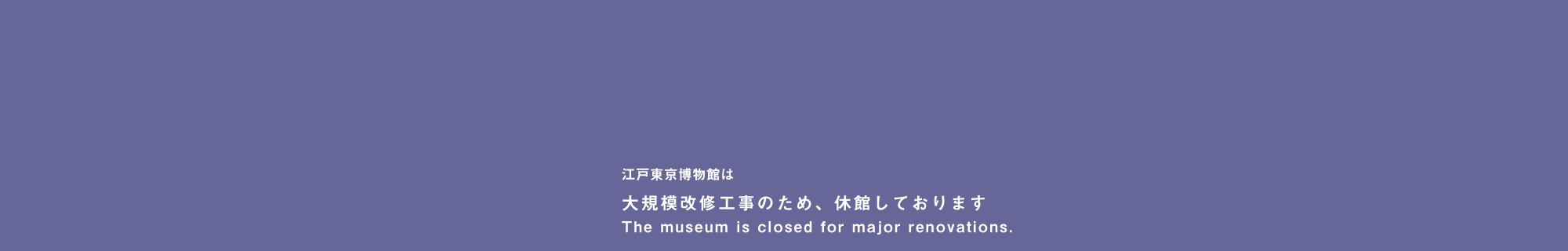
2015/06/08
(回答)
東北大学付属図書館(http://www.library.tohoku.ac.jp/)所蔵『算元記(さんげんき)』に該当と思われる画像あり。下記「国書データベース」83コマ目に確認できる(「玉」に似た字の可能性もある)。これが一般的な例だったか、いつから「正」と書くようになったかについては「回答プロセス」を参照のこと。
国書データベース(国文学研究資料館/)(最終アクセス日:2025/10/10)
URI(https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100237232/)
DOI(https://doi.org/10.20730/100237232)
著作情報(「国書データベース」より)
統一書名:算元記(さんげんき)(Sangenki)
著者:藤岡/茂之(Fujioka Shigeyuki)
成立年:明暦三自序(1657)
国書所在:【版】東北大,東北大狩野(上巻一冊)
(回答プロセス)
『和算の事典』(山司勝紀,西田知己/編集 朝倉書店 2009年11月15日 4191/0019/0009 p.461)によると、この書き方が一般的だったとの記述は見られないが、「現今のような『正』の字が使われるのは明治以降と考えられている」との記述あり。
(レファレンス協同データベース版)http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000098972![]()