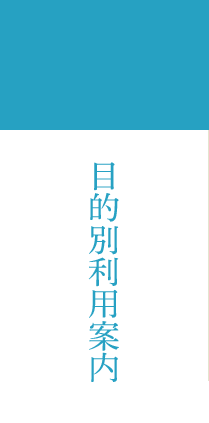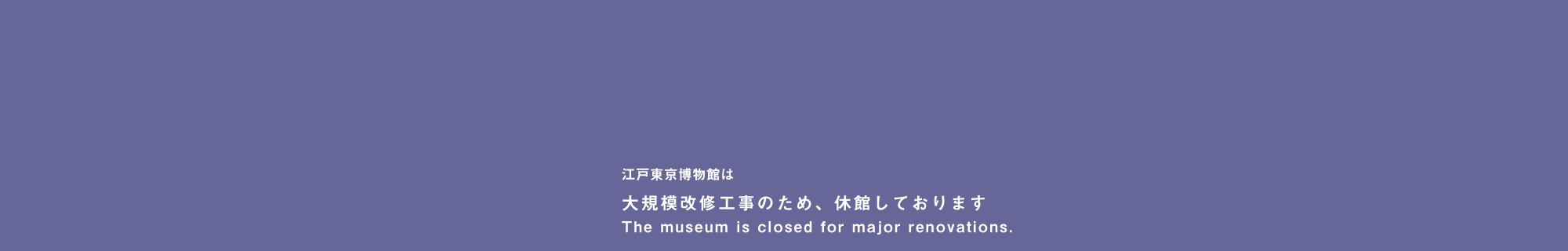
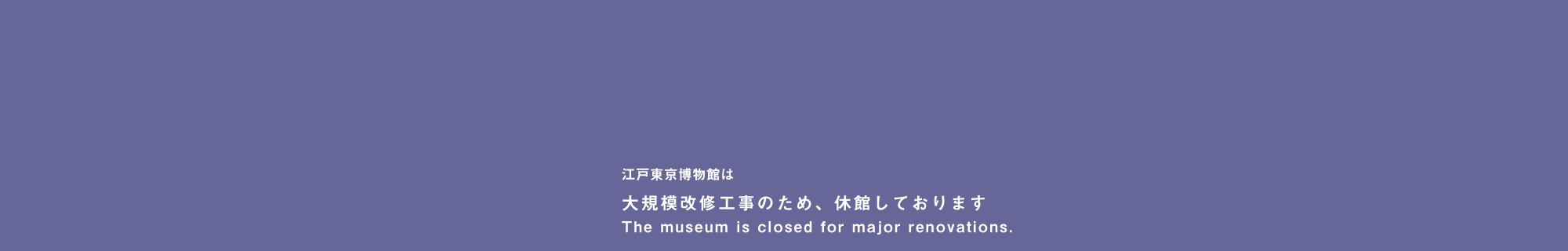
2017/06/29
(回答)
参考資料によると、ガマの油とは切り傷などに効くといわれた膏薬で、販売する際の刀を使った派手な実演や特徴的な口上で知られました。現在よく知られている「筑波山のガマの油売り」の口上は、【資料1】『江戸の大道芸人 庶民社会の共生』によると上方落語にルーツがあり、恐らく昭和初期に関東に伝わってから「筑波山のガマの油売り」となったようです。よって口上も関西版は「伊吹山」、関東版は「筑波山」となります。口上の内容など、詳しくは回答プロセスと参考資料をご参照ください。
(回答プロセス)
薬としてのガマの油の発祥については不明だが、広く世に知られるようになったのは江戸時代以降とみられる。
【資料2】『江戸行商百姿』に江戸時代のガマの油売りの姿が確認でき、薬箱と幟を持っているが、刀を使って実演をしている姿ではない。
(参考資料)
【資料1】『江戸の大道芸人 庶民社会の共生』(つくばね叢書 009)光田憲雄著 つくばね舎 2009年 7797/16/0009 p.161-175 (「ガマの油売り」の成立過程についても検証。)
【資料2】『江戸行商百姿』花咲一男/著 三樹書房1977年 3843/46/77 p.112-113 (ガマの油売りの行商姿の絵がある。)
【資料3】『香具師口上集 新版』室町京之介著 創拓社 1998年 3843/108/98-S00 p.178-185 (伊吹山のガマの油と落語のガマの油を紹介。)
【資料4】『大道芸口上集 新版』久保田尚著 評伝社 1994年 7797/20/94 p.35-40
【資料5】『日本の名薬』宗田一/著 八坂書房 1993年 4998/1/93 p.110-114 (東西の口上について。)
【資料6】『大道芸大全 イラスト事典』馬越ふみあき著 同文書院 1998年 7797/13/98 p.12
【資料7】『日本の伝承薬 江戸売薬から家庭薬まで』鈴木昶/著 薬事日報社 2005年 4997/5/5 p.83-88 (薬品としてのガマの油について。)
(備考)
※1「昔はこんな薬もありました6~『がまの油』他~」(一般社団法人北多摩薬剤師会) http://www.tpa-kitatama.jp/museum/museum_14.html (2017/6/6確認)
(2017/6/6確認)
※2 「ガマの油は何時から筑波山になったか」(日本大道芸・大道芸の会) https://daidogei.info/wp/ (2025/2/18確認)
 (2017/6/6確認)
(2017/6/6確認)※2 「ガマの油は何時から筑波山になったか」(日本大道芸・大道芸の会) https://daidogei.info/wp/ (2025/2/18確認)
(関連事例)
「筑波山ガマまつりのガマの油売りの口上のセリフが書かれている資料はないか。」(牛久市立中央図書館) http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000141586
(レファレンス協同データベース版) http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000185054