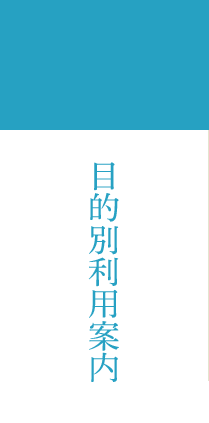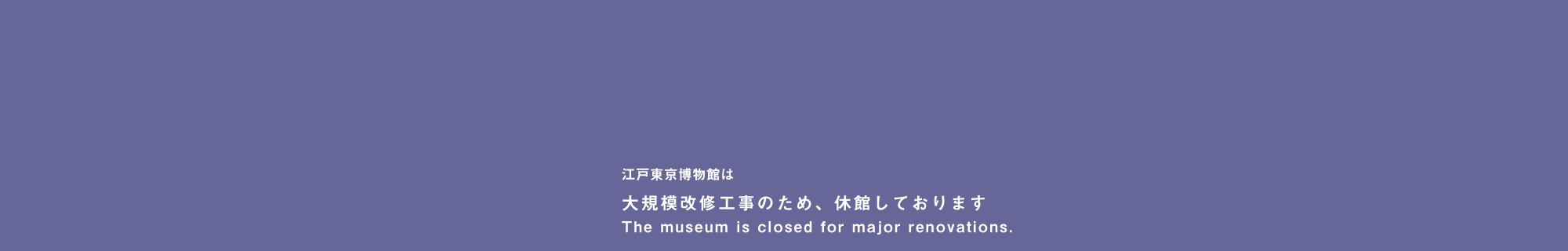
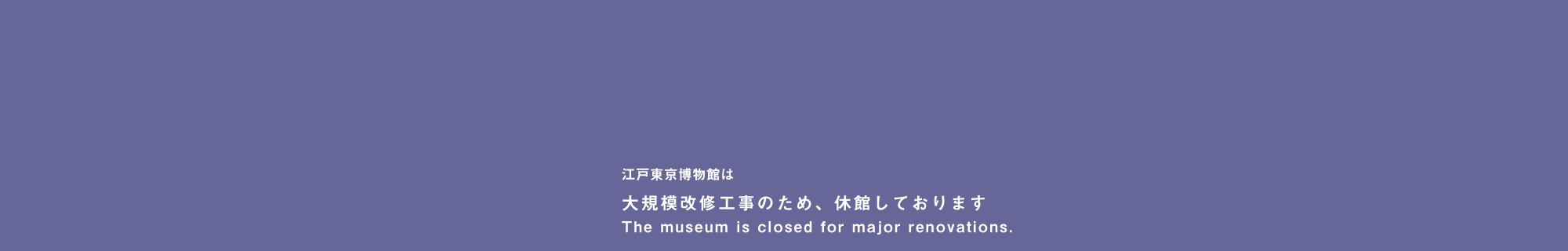
2014年度
140号 2015/02/20
『<通訳>たちの幕末維新』
江戸時代の職業というと、どのようなものを想像しますか? 江戸時代にも、 現代と同様に多様な職業が存在しました。そんな中で、通詞という外国語を 生業とした人たちの事をご存じでしょうか?
この『<通訳>たちの幕末維新』(木村直樹/著 吉川弘文館 2012年 請求記号:2105/1594/0012)では、江戸時代に外国語を 学び、職業とした人たちの奮闘ぶりを伺うことができます。
日本語で記された 参考文献がなかったため、オランダ語を使用して英語を学んだ彼ら。
このような努力を思うと、多様な参考書、多様な機会を得ることができる、 現代の環境のありがたさを感じます。
その反面、LとRの発音の区別が出来ない という、私と同じ苦労を抱えていたことを知ると、時代の隔たりを忘れ親近感を 感じてしまいます。
様々なエピソードに触れ、少し視点を変えて外国語の世界を 覗くことができる1冊です。
139号 2015/01/16
『江戸の寺社めぐり 鎌倉・江ノ島・お伊勢さん』
江戸時代、寺社参りのための旅が盛んに行われました。
参詣地に赴く他、名所めぐりなどの楽しみもありました。
本書では、当時の旅立ちは覚悟の上であったことを踏まえながらも、寺社参詣の旅を文化ととらえ、わかりやすく読み解いていきます。
代表格である伊勢参りだけではなく、武士の聖地としての鎌倉や、江戸において、女性が比較的参詣しやすかった江ノ島にも言及しています。
原淳一郎 著『江戸の寺社めぐり 鎌倉・江ノ島・お伊勢さん』(歴史文化ライブラリー320,吉川弘文館,2011年発行)の他、鎌田道隆 著『お伊勢参り 江戸庶民の旅と信心』(中公新書,2013年発行)、旅の文化研究所 編『絵図に見る伊勢参り』(河出書房新社,2002年発行) も当室でご覧いただけます。
是非、ご来室ください。
138号 2014/12/19
奇妙奇天烈 変わり兜
いよいよ佳境となったNHK大河ドラマ「軍師官兵衛」ですが、黒田官兵衛や長政ら の着用する兜の形が気になった方も多いのではないでしょうか。
戦国時代から江戸時代にかけて花開いた武士の芸術、変わり兜。故事や縁起かつぎ、神仏にあやかりたいといった形の由来は様々ですが、「戦闘の際に頭部を保護する もの」という兜本来の役割から離れ、およそ実戦に向いているとは思えない異形の 数々。ウルトラ怪獣やダースベーダーも真っ青のユニークな造形に驚かされます。
鹿角、兎耳、熊頭、トンボ、蟹、サザエ、釣鐘、逆さまのお椀…そんなモチーフを 頭に被った武将の姿を想像すると、勇ましさにも増してシュールな情景に思わず笑 いがこみあげてきます。
戦国武将所用の逸品から江戸の工芸技術を駆使した珍品まで、変わり兜の魅力満載 な展覧会図録と書籍から、オススメの数冊をご案内します。あれこれと手に取って お楽しみいただけたら幸いです。
『変わり兜×刀装具 戦国アバンギャルドとその昇華』 大阪歴史博物館,産経新聞社 2013年(請求記号:M63 / OS - 24 / 46) 『変わり兜 戦国の奇想天外』神奈川県立歴史博物館 2002年(請求記号:M37 / KA - 6 / 98) 『図説戦国の変わり兜 戦場を駆けた傾奇の美 決定版』 笠原采女編著 学研パブリッシング 2010年(請求記号:7567 / 22 / 010) 『Spectacular helmets of Japan, 16th-19th century(日本のかわり兜)』 Japan Society 1985年(請求記号:7567 / L20 / 85 - E)
137号 2014/11/21
『菊日和 母の日記が語る父との恋とあの頃の東京の暮らし』
著者は女優の波乃久里子となっていますが、母親「久枝」が若き日に書いた日記に 解説を加えまとめたものです。
日記が書かれたのは昭和17年の元旦から4ヶ月ほどで、銀座で友人と映画を観て、 外食を楽しむ姿は、その前年末に真珠湾攻撃があったことや、やがては焦土と化す 東京を想像できないほど穏やかですが、空襲や軍需工場への動員など、徐々に 日常生活が戦争に浸食されていくさまがうかがえます。この時代の銀座の様子は、 現在開催中の企画展「モダン都市銀座の記憶-写真家・師岡宏次の写した50年-」 (11月30日(日)まで)でもご覧いただけます。
久枝は現代歌舞伎に大きな影響を与えた六代目尾上菊五郎の娘です。
よって 登場人物も昭和の歌舞伎史を彩る人物ばかりで、のちに夫となる十七代目中村勘三郎への 想いが日記の中心となっています。彼女がわざわざ清書したとおぼしき日記を残した 真意は推察するほかありませんが、戦時中の若い女性の生活の一端を垣間見るだけでなく、 芸能史としても貴重な記録となっています。
菊日和 母の日記が語る父との恋とあの頃の東京の暮らし』 波乃久里子著 雄山閣 2005年 請求記号:7742 / 204 / 0005
136号 2014/10/17
『江戸看板図聚』
例えば「江戸の物売りのいでたちを調べる」というとき、江戸の板本の挿絵や 浮世絵版画に登場する人物がよりどころになることがあります。
これら江戸時代の 「絵」を現代に再現し、描き表した画家に故・三谷一馬がいます。
その作品は 『江戸商売図絵』『彩色江戸物売図絵』などの本になっています。
さて、「もう新しい本は出ないのだろう」と思っていましたが、ご子息が 編者となって新たに出版されたのが今回の『江戸看板図聚』(中央公論新社・2013年) です。
これは書名からわかるとおり江戸時代の看板を描きあつめた1冊ですが、 温故知新、現代の看板に通じるところもあり、何より見ていて楽しくなります。
すべてに出典が記されているので、原典に当たっていくこともできます
135号 2014/09/19
やんごとなきお屋敷めぐり
当館と同じ財団が運営する“東京都庭園美術館”をご存知でしょうか?
朝香宮の邸宅として1933(昭和8)年に竣工し、現在は美術館として保存・公開 されています。
設計は宮内省内匠寮、内装は1925(大正14)年パリで開催された現代装飾美術・ 産業美術国際博覧会(通称:アール・デコ博覧会)で多くのパビリオンを手掛けた アンリ・ラパンを筆頭に当時を代表するデザイナーの作品であふれています。
庭園美術館は平成23年から約3年間にわたる改修工事を経て、今秋リニューアルオープン します。日本の“アール・デコの館”を是非訪れてみてください。
本書には他にもホテルや旅館、大学施設などとして現存している建物が 紹介されています。贅を尽し、洗練された空間を体感できるのは現代だからこそ。 みなさんも古地図を片手に散策してみてはいかがでしょうか?
普段見慣れた景色がまた別の顔をみせてくれます。
『別冊太陽 太陽の地図帖009 古地図で歩く天皇家と宮家のお屋敷』岡本哲志/監修 2011年9月 平凡社 P58~ 旧朝香宮邸(現:東京都庭園美術館)が紹介されています。
上記資料以外にも当室では様々なテーマで編集された古地図の本を所蔵しています。 歴史散歩にお役立てください。
133号 2014/07/18
『寺社の装飾彫刻 宮彫り‐壮麗なる超絶技巧を訪ねて‐』
老若男女問わず仏像巡りをされる方は多くいらっしゃいますね。
国宝や重要文化財に指定されている木彫の仏像は、鎌倉時代までのものが殆どです。
そこで江戸時代の木彫は見過ごされてしまいがちですが、城郭や住まい、寺社など、建築物の装飾彫刻には、見事な木彫が数多く見られます。
『寺社の装飾彫刻 宮彫り‐壮麗なる超絶技巧を訪ねて‐』 (若林純 撮影・構成,日貿出版社,2012年発行) は、江戸の彫物大工が残した装飾彫刻の傑作が700枚もの写真で紹介されています。
それは、人や動物が、副題のとおり、超絶技巧で表現され、何ともユーモラスな表情をしていたり、鮮やかな色彩であったり、今にも動き出しそうで魅力を感じずにはいられません。
装飾彫刻自体が大きく写し出されているので、 細かい部分もじっくり見ることのできるオススメの1冊です。
2014/06/20
和算に挑戦
さて問題です。
「キジとウサギが合わせて50疋(ひき)います。足の合計は122本です。キジとウサギ、それぞれ何疋いるでしょう?」
連立方程式を知っている中学生であれば、x、yを用いて簡単に解いてしまうであろうこの問題、江戸時代には“鶴亀算”で解答を導きだしました。
『和算に挑戦10周年記念誌』は、一関市博物館が2002年から開催してきた和算問題を出題するイベントの解答解説集です。初級(小学生以上)中級(中学生以上)上級(高校生以上)の全30問。問題の出典となる江戸期の算術書や算額(数学の絵馬)の解説を見ると、和算が日本独自に、そして高度に発展してきたことに驚かされます。
上述の「キジとウサギ」は、江戸期の算額を元に出題された初級問題のひとつ。江戸と現代での算術の違いも含めて、解答へのアプローチは幾通りもあります。
答えが気になった方は、ぜひ7階図書室でご確認ください(*)。このほか、杉算、油わけ算、盗人算…など興味深い和算の入門には、下記の図書も併せてオススメいたします。
『和算に挑戦 10周年記念誌』一関市博物館 2013年 請求記号:M22 / IC - 1 / 33
『江戸の「算」と「術」』佐藤健一著 研成社 2008年 請求記号:4191 / 13 / 008
『子どもたちは象をどう量ったのか?』西田知巳著 柏書房 2008年 請求記号:3721 / 141 / 008
(関連サイト)
一関市博物館「和算に挑戦」http://www.museum.city.ichinoseki.iwate.jp/wasan
*「キジとウサギ」の解答例は、平成20年度初級問題として上記ウェブサイトでもご覧いただけます。
国立国会図書館 電子展示会「江戸の数学」http://www.ndl.go.jp/math/
131号 2014/05/16
『すしの本』(篠田統著 岩波書店 2002年 請求記号:5962 / B103 / 0002 )
「元来は東南アジア山地民の料理法、否、米を利用した川魚や鳥獣肉の貯蔵法なのだ。」
とのはじまりから、「え?」と引き込まれてしまいます。
本書は「すし」についての、古今東西の文献やフィールドワークから得た膨大な研究を 分かりやすい文章でまとめた名著(昭和45(1970)年刊)の復刻文庫版です。
「すし」と聞くと江戸前ずしを想像してしまいがちですが、稲荷ずし、太巻きずし、 馴れずし等々、日本の食文化に浸透して歴史を重ねた「すし」の定義は広く、その形態は様々であることに気づかされます。
今やSUSHIとして世界中で食べられている「すし」。昨年、ユネスコ無形文化遺産とし 和食が登録されたことからも、今後、重要な研究分野のひとつになるのではないでしょうか。
冒頭の起源説についても諸説あり(『すしの事典』日比野光敏著 東京堂出版 2001年 請求記号:3838 / 161 / 001)、まだまだ研究の余地があるテーマと言えるでしょう。
130号 2014/04/18
『明治時代史大辞典』
時代別の歴史辞典をよく目にするようになりました。
昨年完結した『明治時代史大辞典』(全4巻)もそのひとつです。この辞典は、わが国最大の日本史辞典である『国史大辞典』(全15巻17冊)と同じ出版社、 吉川弘文館から刊行されています。
さて、明治時代―思いつくまま、あることばを引いてみたのですが…執筆者が別で、書かれている内容に違いがあり…権威ある『国史大辞典』からの単なる引きうつしではありませんでした。
両方使うことで「調査」に厚みと広がりを持たせられ、より多くの ヒントを得ることができるはずです。併用したいと思います。
『国史大辞典』に未収録の項目も新たに多数収載ということで、どんなことばが 入っているのか、これもまたゆっくりとみていきたいところです。