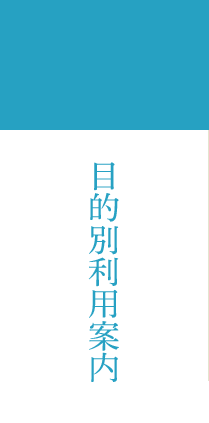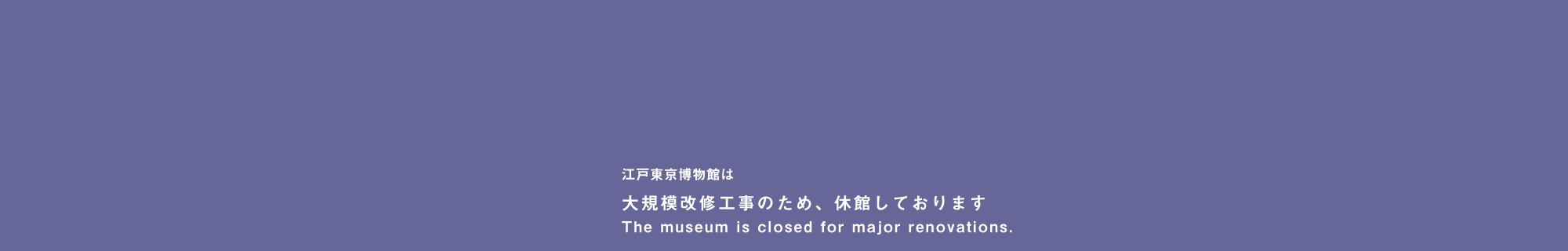
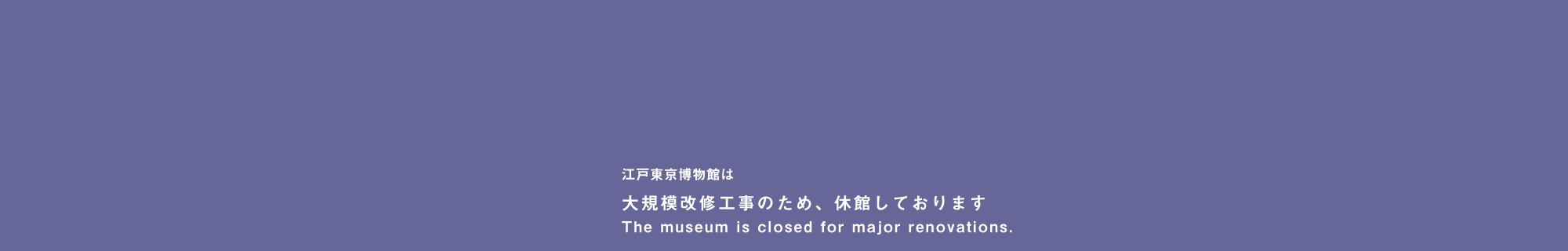
2005年度
35号 2006/3/17 (江戸東京博物館ニューズレター 54号)
日本の伝統色
「アメジスト」と言って、どんな色か即座に思い浮かびますか?
たとえば自動車や家電品のカタログに、色−アメジストと書かれていたら。現代においては商品のカラーバリエーションが豊富で、色名だけではわからず、現物を見て「ああ」などということが多々あります。
一方、「江戸紫」はどんな紫だかわかりますか?
文字どおり江戸の代表色のひとつと言ってよいと思いますが――江戸時代あるいはそれ以前からある日本古来の色名も、その名前を聞いただけではわからないものが多数あります。
『日本の傳統色』(長崎盛輝著・京都書院・1996年・請求記号7573/B6/96)は、文庫の体裁でありながら、巻頭に色票のページ、また巻末にもカラーチャートのページを設けていて、目にたのしい一冊です。
そして、本文では色票の番号(色名)ごとに、古文献などを駆使してその色について説明を施しています。
今日使われる横文字の色名がどんな色かを知ることも必要ですが、日本古来の色名こそ残しておきたいものです。
本書によれば、アメジスト=江戸紫です。
(関連サイト)
粋屋(日本の伝統文様と伝統色) http://www.ikiya.jp/![]()
和色大辞典 http://www.colordic.org/w/![]()
34号 2006/2/17 (江戸東京博物館ニューズレター 53号)
いつの時代も頭の痛い受験勉強
また受験シーズンがやってきました。
厳寒の冬となってしまった今年、受験生の皆さんも風邪などひかないようにがんばってほしいものですね。
さて、図書室にも明治末や大正、また太平洋戦争中の“過去問”(過去入試問題集)が数冊ほどありますが、いつの時代も受験勉強はなかなか厳しいものだったことが伺えます。
『増訂入学試験作文模範答案集』(武田芳進堂・発行)は、大正期に出版された全国の中学校・女学校・実業師範学校・陸軍幼年学校などの受験準備用の参考書です。口語体や文語体、候文体の表現に、難しい漢字も数多く使われ、テレビやマンガを楽しみに育ってしまった私には、10〜12歳くらいの子供を対象に書かれた筈の模範解答を読むのも一苦労。
“文章上達の秘訣は多く読み、多く作り、多く考へるにある。是を三多と謂ふ。”
・・・なるほど、作文に限らず勉強に近道はありませんね・・・
33号 2006/1/20 (江戸東京博物館ニューズレター 52号)
江戸の坂、東京の坂
江戸の地図の上、道に梯子のような段々や△・▽(さんかく)が書いてあったら、それは坂道の印です。神楽坂や芋洗坂、道玄坂に九段坂など、江戸から現在にその名を残す坂道も数多くあります。
富士山が見えれば富士見坂。海が見えるのは潮見坂。
墓地のそばの幽霊坂に、木々が茂って薄暗いのは暗闇坂。
大きな坂は大坂で、急な坂は胸突坂。
江戸の庶民が名付けた坂の名前は、江戸っ子気質そのままで「単純明快、即興的で要領よく、理屈がなくて、しかもしゃれっ気があふれている」と『江戸の坂 東京の坂』(有峰書店'70)の著者、横関英一氏は書いています。
現在では町並や景観も大きく変化し、江戸中いたるところにあった富士見坂も、実際に富士山を眺めることができるのは、日暮里の富士見坂のみになってしまったようです。
カメラ片手に坂道をめぐる坂道愛好家が、じわじわと増えていると聞きますが、江戸っ子に対抗して、身近な坂道に好きな名前をつけてしまうのも楽しいかもしれません。
○江戸の坂道関係図書
・『江戸の坂 東京の坂』(横関英一/著 有峰書店'70)
・『続 江戸の坂 東京の坂』(横関英一/著 有峰書店'75)
・『江戸東京坂道事典』(石川悌二/著 新人物往来社'98) 他
32号 2005/12/16 (江戸東京博物館ニューズレター 51号)
大名気分でお正月
ひとくちに「雑煮」と言っても、思い浮かべる味は様々。
雑煮は非常に地域の特色がある料理と言われています。
東京の雑煮は、鶏肉入りで、醤油味、それに青菜などを添えたものが一般的です。しかし、京都では白味噌仕立てが普通だとか。また、餅の形も丸、角と様々ですし、小豆あん入りの餅や、反対に餅を入れない地域もあるそうです。
もっとも、最近では正月に雑煮を食べる家庭が少なくなっているとも耳にします。おせち料理に代わって、デパ地下、コンビニ、ファミレス、ファストフード・・・正月から開店している店がたくさんあるのだから、外食で済ませる方が楽。
これが現代日本の正月料理と言えるかもしれません。
とはいえ、せっかくの正月だから料理に懲りたい、という方なら、江戸時代の正月料理の再現に挑戦してみてはいかがでしょうか。
『再現江戸時代料理 食養生講釈付』(松下幸子,榎木伊太郎/編集 小学館 5962/77/093)には、雑煮から大名の正月料理まで載っています。もちろんそれ以外の料理も、意外に簡単で健康的です。
それでは、食べ過ぎにはくれぐれもご注意の上、良い年をお迎え下さい。
(※カッコ内数字は請求記号)
31号 2005/11/18 (江戸東京博物館ニューズレター 50号)
『これを判じてごろうじろ』
お笑いブームが続いているそうで。
唐突ですが、おやじギャグ、嫌いですか? あるいは好きですか??
江戸時代の刷り物に、判じ物(判じ絵)があります。
判じ物とは、絵を使ってあらわした言葉(?)を何と読むかというもので、例えば「東海道五十三次はんじ物」という刷り物の中を見ると、2冊の本の表紙に「は」の字が4つ書いてあって「日本橋」(=2本は4)と読むとか、尾の生えている俵に濁点がうってあって「小田原」(=尾俵)と読むとか…かなりのくどさ。おやじ入ってます。好きな人にはたまらないでしょう。
1999年に「たばこと塩の博物館」で、判じ物の企画展が行われました。
このときの図録『これを判じてごろうじろ〜江戸の判じ絵』には、判じ物がたくさん収められています。見ていたら、笑うより、そのくどさが目にしみて泣けてきました。
なお、この図録をもとに2004年に小学館から『江戸の判じ絵 これを判じてごろうじろ』が出ました。近々当室にも入る予定です。それでは、まままままままままま…(「ま」が「多」いので、ま多=また。くっくどい)。
30号 2005/10/21 (江戸東京博物館ニューズレター 49号)
『別冊太陽 日本を楽しむ暮らしの歳時記』
秋も深まり、北の山上から山装う季節となりました。
『別冊太陽 日本を楽しむ暮らしの歳時記』は春夏秋冬号の4冊、2000語にも及ぶ季語が美しいカラー図版と共に掲載されています。
ようやく色づきだした“薄紅葉”、
見事に彩られた“野山の錦”、
散り行く“黄落”。
盛りだけではなく、季節の移ろいを愛で慈しむ。
季節感が薄れつつあるといわれて久しくなりますが、秋の夜長、研ぎ澄まされた感性としなやかな表現で綴られた歳時記を、たまにはゆっくり眺めて過ごしたいものですね。
29号 2005/9/16 (江戸東京博物館ニューズレター 48号)
さァてお立ち会い 香具師口上集
「さァてお立ち会い。ご用とお急ぎのない方がございましたらゆっくりと話を聞いてごろうじろ」とはじまるガマの油売りの口上。
トトンタンッと膝を打つようなリズムで「さァ買った、買った」と、威勢よく啖呵(たんか)を切るのはバナナの叩き売り。
金魚売りに竿竹屋、哀愁漂う手風琴にのせた薬売りの売り声。
「アさて さてさてさてさて」は南京玉簾。
お腹から声を出してしゃべってみたくなるような売り声、口上の数々に、聖徳太子から寅さんまで、香具師(やし)の歴史をそれこそ口上のように軽妙な文体で説くのは『香具師口上集 新版』(室町京之介著 創拓社)。
今村恒美さんによる挿絵からは江戸の風情が漂います。
「結構毛だらけ猫灰だらけ。見上げたもんだよ屋根屋のフンドシ。
見下げたもんだよ底まで掘らせる井戸屋の後家さん。
上がっちゃいけないお米の相場、下がっちゃ怖いよ柳のお化け。。。」
ほら、啖呵を切りたくなってきたでしょう?
28号 2005/8/19 (江戸東京博物館ニューズレター 47号)
怖いけど読みたい!
『リング』や『呪怨』など、ハリウッドで日本のホラー映画がリメイクされ、ヒットが続いています。今や、ホラー映画はアニメや漫画と並んで、世界が注目する日本文化と言えます。
日本ホラー映画の「ジワジワと怖い」と言う特徴は、日本に古くからある「怪談」に根ざしていると考えるのは、それほど的はずれではないでしょう。
単にお化けが出てくるだけではなく、人間の業や欲、因果を巡って展開する心理的サスペンス要素が強い作品が、特に大衆の支持を得てきました。
江戸から明治を生きた落語家の三遊亭円朝は、そんな傑作怪談噺を世に送り出し、語るだけでなく、文学としても残しました。
『怪談牡丹灯篭』『真景累ヶ淵』(岩波文庫)などがそれです。
しかし、円朝は怪談が専門だった訳ではなく、人情噺の名作もまた数多く残しています。
怪談噺にも、ただ「怖い」だけではない人間の心の機微を、巧みに織り込んでいるのです。
『怪談牡丹灯籠』が面白いと感じたら、『世界大衆文學全集 第35巻 世界怪談名作集』(リットン/他著 岡本綺堂/訳 改造社)もお薦めです。
『怪談牡丹灯籠』の下敷きになったといわれる『牡丹燈記』が収録されています。
※青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/![]() )では円朝作品、
)では円朝作品、
『世界怪談名作集』の一部がwebで読めます。
27号 2005/7/15 (江戸東京博物館ニューズレター 46号)
ビールと日本人
おいしい季節がやってきました。あんな苦いもの、どこが?という方もいるとは思いますが。ビール!
日本で飲まれ造られるようになってから、たかだか百数十年の歴史しかありませんが、ビールは数あるお酒の中でも消費量第1位だそうです。
『ビールと日本人』には、いろいろな資料を駆使してビールの日本(人)への普及の歴史がつづられています。
表紙カバーには、田舎から出てきた男ふたりがビアホールではじめてビールを飲む様子を描いた北沢楽天の漫画(明治35年)が使われています。
ひとりが「これが麦酒(ビール)ていのか、えらく泡ア立てるが是れ喰ふのかな」と言えば、ひとりが「ナーニ泡喰ッちやいけねえ、そりや熱燗(あつかん)のせいだよ」と返す。
しかし、一口飲むとふたりとも「ヒヤーこりや冷(ひや)だ、おまけに苦げいや」と顔をしかめたり、怒ったり。
これをみると、明治30年代になっても全国までは普及していなかったんですね。都会でもまず飲みだしたのは軍人や役人といったエリートたちとか。高級酒だったようです。
とはいえ、幕末、幕府留学生の榎本武揚・西周が飲む、薩摩の小松帯刀が飲む、そして福沢諭吉が……本文中、そんな資料も紹介されています。
この本は、元は麒麟(キリン)麦酒から出版の非売品でしたが、1984年に三省堂、1988年に河出文庫から市販されています。
さて、書き終えたところで一杯……行って来ます。
(※関連サイト)ビール酒造組合 http://www.brewers.or.jp/![]()
26号 2005/6/17 (江戸東京博物館ニューズレター 45号)
大相撲
昭和の花形力士・元大関貴ノ花、二子山親方が55歳の若さで亡くなりました。
小柄ながら、自分よりも一回りも二回りも大きなお相撲さんに挑み、白星を挙げる数々の名勝負は、相撲ファンならずとも印象に残るものでした。
そんな名勝負を写真・解説・実況で楽しめる本が『大相撲』(日本相撲協会/編 小学館 1996年発行)です。
日本相撲協会設立70周年を記念して発行されたもので、名勝負だけではなく、稽古や巡業の様子、相撲にまつわる品々などの豊富な図版、年表などの資料も充実しています。
国技館の土俵に力士を始め、行司、呼出し、日本相撲協会関係者が一堂に会している(男性だけですが)集合写真は圧巻です。
その他、図書室には相撲の歴史の本や、江戸博のお隣、国技館の中にある相撲博物館の紀要も所蔵しています。
(関連サイト)(財)日本相撲協会 http://www.sumo.or.jp/![]()
25号 2005/5/20 (江戸東京博物館ニューズレター 44号)
数にまつわるあれこれ
丁前、二八蕎麦、三種の神器、四方山話、五穀、六地蔵、七福神、大八車、九分九厘、十二支、東海道五十三次、日本百景・・・
数のつくことばはたくさんありますが、いざその意味や語源、項目を問われるとなかなか即答できません。
そんな数にまつわることばを調べるときのお役立ちツールが、『名数数詞辞典』(東京堂出版'80)と『数のつく日本語辞典』(東京堂出版'99)です。
どちらも零から無限まで、数順にことばが並んでおり、ぱらぱら眺める雑学本としても楽しめます。「江戸の三大祭り」「江戸の七不思議」「大東京百観音」など 江戸東京に関しては『角川日本地名大辞典13東京都』(角川書店'91)
巻末の“東京都地名名数一覧”も併せてどうぞ。
24号 2005/4/15 (江戸東京博物館ニューズレター 43号)
ランキングを通してみる江戸時代
「あなたが不要だと思う物の順位を挙げてください」と言われたら、どんな物を挙げるでしょうか?
テレビや雑誌では連日のごとく、いろいろなランキングが発表されています。しかし、これは何も最近になって始まったわけではありません。実際、先述の様なランキングは「不要競」として、江戸時代に発表されています。「見立番付」と名付けられたこれらは、人々の情報源の一つとなりました。「温泉」「名所」「美味」など、現代でもお目にかかれるような、楽げな番付だけでなく「儲かる商売」「名医」などという、辛口の番付もあったようです。現代のランキングと比べてみるのも面白いかもしれません。
他にどんな番付があったのか、興味が沸いた方は
『番付で読む江戸時代』(林英夫・青木美智男著、柏書房)
『大江戸番付づくし』(石川英輔著、実業之日本社)をご覧ください。
ちなみに「不要競」は『大江戸番付づくし』に載っています。