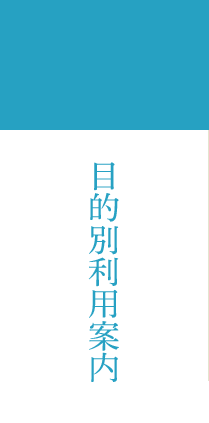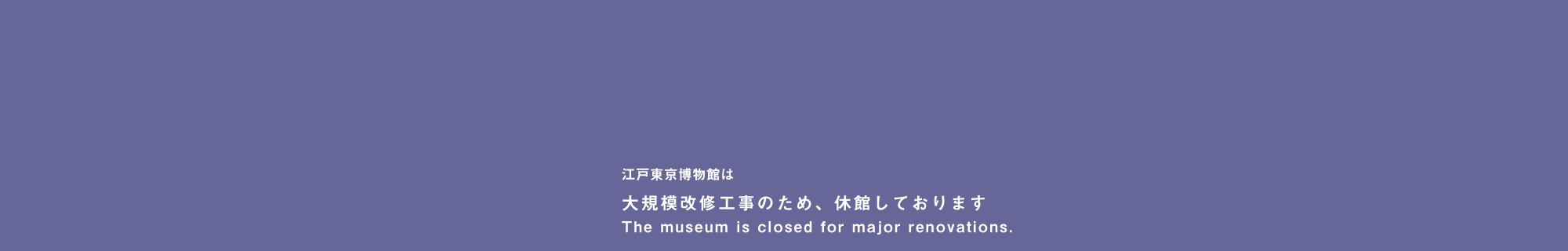
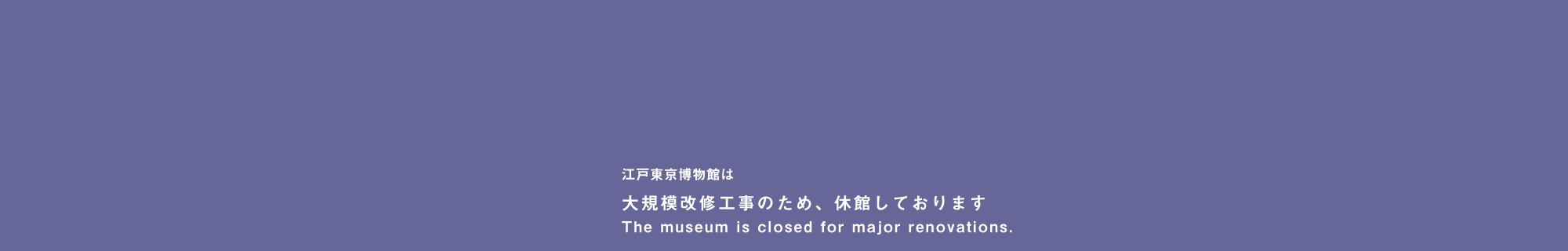
2003年度
11号 2004/3/19 (江戸東京博物館ニューズレター 29号)
江戸の地名を調べる
江戸時代の地名は現在のどこかという、古い地名についてのご質問は、年間通して絶えません。地名というのは思った以上にたくさんの情報をもたらしてくれる、貴重な歴史の鍵だと思います。
こういった疑問のほとんどは「地名辞典」の類で解決しますが、江戸の地名を調べる際、読み物としても、辞典としても楽しめる好著が『江戸・町づくし稿(全四巻)』(岸井良衛著、青蛙房刊)です。
土地の歴史から地名の由来や出典まで簡潔に記載してあり、重宝な一冊となっています。
しかし、江戸時代まで遡らなくとも、すでにわからなくなっている地名も珍しくありません。地名変更がやむを得ないのならば、誰かがしっかりと記録を取っておかなければならないのではないか、そう思わずにはいられません。
10号 2004/2/20 (江戸東京博物館ニューズレター 28号)
モノの名称を知る
「ほら、あれ何だっけ?ふすまを開け閉めするときに手を掛ける、丸いあの…」
言葉が出てこないのは、歳のせい(?)ばかりではないでしょう。
ふだん、何気なく目にしたり、手にしたりしているモノの名称、ことに部分名称は、意外なほどわからなかったりします。
昔のモノとなれば、なおさらです。
これにこたえてくれる本として、
1『全図解モノの呼び名がわかる事典』(日本実業出版社)
2『モノの名前大図鑑』(ワニマガジン社)
3『モノの名前がズバリ!わかる本』(河出書房新社)の3冊が、
たまたまなのでしょうが、まとめて1999年に出ています。
もちろん万物についてというわけにはいきませんが、1・2は図解もあり、とくに1は第1章「文化編」が江戸時代のモノを調べるのにも使えそうです。
雑学に、見て読んで楽しい本です。
さて、「ふすまの開け閉めのときの丸いあれ」ですが…こたえは「引手穴」です。
9号 2004/1/16 (江戸東京博物館ニューズレター 27号)
日本橋を読む
江戸開府400年の昨年は、江戸東京の歴史を振り返りつつも、東京の今を見つめるさまざまなイベントが開催されましたね。
図書室でも「江戸を読む」コーナーを設けたり、講座を開催したりと、はじめての試みを行いました!
徳川家康が幕府を開いた慶長8年(1603)は、江戸の町に日本橋が架けられた年とも言われています。
さて、外はまだ寒い冬・・・暖かい部屋で、江戸開府401年目のはじまりに日本橋を舞台にした文学作品を、読んでみてはいかがでしょう?
まずは長谷川時雨の回想録『旧聞日本橋』(昭和46年 青蛙房発行 9146/101/71)。
作者の生まれ育った明治前期の日本橋界隈と、ゆかりの人々の逸話を満載。
登場人物のセリフに、なんだか懐かしさを感じます。
次は田山花袋の『東京の三十年』(大正6年 博文館発行9146/382/17)
南伝馬町の書店に丁稚奉公をしていた花袋少年は、江戸の面影と文明開化の風景が共存する、日本橋付近の様子を見ました。花袋の立身出世の物語です。
そして、日本橋区蛎殻町生まれの谷崎潤一郎も、『幼少時代』(昭和32年 文芸春秋新社発行 9102/143/57)で、少年期の思い出を語っています。
日本橋は明治44年(1911)に現在の石造の橋になりましたが、その後の日本橋付近を舞台にした作品としては、泉鏡花の『日本橋』(大正3年 千章館発行 9102/14/14)がお薦めです。花柳界の芸妓を取り巻く男たちの姿と因縁が描かれた作品。とは言っても、自働電話(≒公衆電話・・・最近少なくなりました)や路面電車といった新時代の都市の風物が登場します。
そして戦後、首都高速道路が覆いかぶさった直後の日本橋は、開高健の『ずばり東京 昭和著聞集 上』(昭和39年 朝日新聞社発行9146/124/1)を一読ください。
「“渡る”というよりは、“潜る”という言葉を味わう」「空も水も詩もない日本橋」と記す、作者の嘆きが聞こえてきます。週刊誌に連載された、この東京ルポルタージュは、今読んでも新鮮です。
8号 2003/12/19 (江戸東京博物館ニューズレター 26号)
時代劇のお供に
(時は将軍家光の世。岡っ引きが朱房の十手を手に、居酒屋の縄のれんをくぐりながら・・・)
「親父、熱いのを一本つけてくれ」
・・などという時代劇があったら、それは時代考証家がいないドラマだと思ってさしつかえないそうでです。
今回ご紹介するのは、『天皇の世紀』や『伝七捕物帖』を始めとする数多くの時代劇に携わり、江戸文学浮世絵研究家でもあった林美一著『時代風俗考証事典』(河出書房新社刊)。
江戸時代の風俗に関しては『三田村鳶魚全集』(全28巻 中央公論社刊)という名著がありますが、本作はよりコンパクトに、写真図版が多く出典が明記してあるという点でも、初心者にも親しみやすい好著です。
しかも、時代考証家がどういった仕事をしているのかを、ドラマ作りの裏話も交えながら綴っているので、歴史に興味がない方でも楽しめるでしょう。
ここで述べられているのは主に昭和40年代頃のテレビ界ですが、その当時でも既に時代考証がかなりいい加減になっている事を、再三林氏は嘆いています。確かに、重箱の隅をつつく様な考証はドラマを停滞させるだけであるけれども、考証がしっかりしていればドラマに新しい発見が生まれ、より深みを増すはずであるという意見には大いに頷かされます。
時代考証家の著書は他に『時代考証事典』(稲垣史生著、新人物往来社)などがあります。
年末年始は時代劇が多く放送させるはず。時代考証家になったつもりで、ご覧になってはいかがでしょうか。
7号 2003/11/21 (江戸東京博物館ニューズレター 25号)
『化粧ものがたり 赤・白・黒の世界』
(高橋雅夫/著 雄山閣出版/刊 1997年)
女性であれば誰でも、きれいになりたいという願望を少なからず持っているのではないでしょうか?
女性誌のコスメ特集を熟読し、秋の新色をチェック。○○のファンデーションがよいと聞けばデパートに走り、100円ショップのヒアルロン酸があなどれないと大量に買いだめする人もいるとか。
そんな女心は昔も同じ。黒髪を長く伸ばし、おしろいを塗り、紅をさす。女性たちは、より美しくあるために努力を重ねました。
『化粧 ものがたり 赤・白・黒の世界』は、「赤の章 赤色顔料と紅のものがたり」、「白の章 おしろいのものがたり」、「黒の章 眉化粧とお歯黒のものがたり」の3部構成。
日本の伝統的化粧は「赤・白・黒」の3色配色から成り立ち、この配色は日本人の美意識から生み出されたとの観点で、古代から現代までの日本の化粧史がわかりやすく書かれた一冊です。
鉛白粉による鉛中毒や眉化粧の変遷、白髪染めの元祖の話など興味深いものばかり。なかでも「お歯黒おばあさん訪問記」は必見。昭和52年取材時、御年96歳の女性がお歯黒をつけている様子を写真で紹介しています。お歯黒は虫歯と歯槽膿漏の予防に良いそう。チャレンジしてみる?
6号 2003.1.10.17 (江戸東京博物館ニューズレター 24号)
おもわず「へえー」
『年齢の事典 その時何歳(いくつ)?』(阿部猛/編 東京堂出版1999)
自分と同じ年齢の人が気にかかること、ありませんか?
美術展で作家の略年譜を見ても、「私と同じ歳でこの人はこんなに活躍していたのねぇ」とか「4度目の結婚をしている!」と、つい自分の年齢のところに注目してしまったり。
『年齢の事典 その時何歳(いくつ)?』(阿部猛/編 東京堂出版1999)は、当事者の年齢ごとにできごとが配列されており、たとえば‘27歳’の項にあるのは
「織田信長が桶狭間で今川義元の軍を破る(1560年)」「力道山が力士からプロレスラーに転向(1951年)」「夏目雅子病没(1985年)」などなど。
とりあげられているのは歴史上の人物から現存の方まで約1400名。ちなみに年齢項目は2歳から最高齢140歳(!)まであります。
自分史を書くことが流行していると聞きますが、さまざまある伝記や年表などから気になる人物やできごとをひろい集めて、自分なりの「他人年齢表」をつくってみるのもおもしろいかもしれません。
5号 2003/9/19 (江戸東京博物館ニューズレター 23号)
モノの値段の移り変わり
『値段の明治・大正・昭和風俗史』週刊朝日編(1981年/朝日新聞社)
今回ご紹介するのは、当館図書室の日々のレファレンスでも大いに活用している「ものの値段」の本です。
各界著名人のさまざまな「もの」や「サービス」にまつわるエッセイと、その項目ごとの「値段年表」により、ものの値段を介して日本人の暮らしの変遷を探っています。
例えば、女優の沢村貞子さんは子どもの頃育った浅草での「しる粉」の想い出を、作家の永井路子さんは新婚時に夫に贈った「レコード」の想い出を綴っているといった具合。
連載時から(1979年より1983年まで『週刊朝日』にて連載)かなり好評だったらしく、「続」「続続」と単行本化されています。
また、エッセイの読み応えもさることながら、一緒に付された「値段年表」は資料として大変便利な代物です。
あとがきを読むと、過去せいぜい百年のこととはいえ、資料の収集はとても困難だった様子がうかがえます。取り扱っている項目の選択それ自体も、興味深いラインナップです。
さてさて、まだ働き盛りだった頃の祖父が晩酌に飲んだ瓶ビールの値段はいくらだったのかしら?
4号 2003/8/15 (江戸東京博物館ニューズレター 22号)
古文書をマイクロフィルムで読もう
「古文書」というとどんなイメージを持ちますか?
「かび臭い」「扱いが難しい」と、近寄りがたいイメージを持たれる方が多いと思います。
確かに古文書は文字通り古い、貴重な史料ですから、専門家でも扱いに苦労しますが、マイクロフィルムに収められた古文書ならば、初心者でも簡単に見ることができます。
図書室では多くの古文書をマイクロフィルムとして保存していますので、初心者の方から上級者の方まで、何かしら興味を持てる古文書と出会うことができるのではないでしょうか。
判読には『図録古文書入門事典』(若尾俊平編,柏書房)
『入門近世文書字典』(林英夫・中田易直編,柏書房)
『基礎古文書のよみかた』(林英夫監修,柏書房)等をご利用ください。
マイクロフィルム一覧、利用方法は図書室ホームページをどうぞ。
3号 2003/7/18 (江戸東京博物館ニューズレター 21号)
『戦後文化の軌跡 1945-1995』
(目黒区美術館ほか/編 朝日新聞社/発行)
博物館や美術館の展覧会会場で展覧会図録をご覧になることも多いかと思います。
でも、街中の書店や図書館ではあまり見かけないのではないでしょうか。
最近は出版社から書籍として発行される場合もありますので、普通の書店に並ぶこともあるのですが、大部分は各博物館や美術館が展覧会用に作り、展覧会期間中に会場で頒布することを一番の目的として、限られた部数を発行します。
そのため、書店の流通にのらないことも多いですし、図書館でも網羅することは困難です。
その展覧会が終わってしまうと、なかなか見る機会を得られない展覧会図録ですが、書籍としてはかなり優れものが多いのです。
いろいろなジャンルのテーマを様々な切り口から企画している展覧会の図録は、豊富な図版にわかりやすい解説や資料がついているものが大多数、ちょっと専門的な論文を読むこともできますし、未発表や新発見の資料が載っていることもあります。
最近では子供向けに作られた楽しめる図録や、デザイン性の高い凝った装丁の図録も少なくありません。
展覧会は図録という形で残り、その時代をうつすものとも言えるでしょう。
タイトルに挙げてあります『戦後文化の軌跡 1945-1995』は、美術、写真、建築、デザイン、ファッション、いけばな、映像、出版、マンガ等々、戦後をあらゆる視覚文化から検証した展覧会の図録です。
大量の図版にジャンルごとの解説やコラムも見応え、読み応えがあるのはもちろん、戦後文化史年表や参考文献も充実しています。
江戸博図書室に来れば、このような各地で開催された過去の展覧会図録が必ず見られる、と堂々と言えるくらいコレクションを充実させたいなあ、と思っている今日このごろでした。
2号 2003/6/20 (江戸東京博物館ニューズレター 20号)
『夢の江戸歌舞伎』
(服部幸雄/著 一ノ関圭/絵 岩波書店発行)
江戸の芝居小屋「中村座」。文化・文政期の中村座が劇場の表から裏までたっぷり描かれ、江戸歌舞伎の醸し出す高揚を味わうことができるのが『絵本 夢の江戸歌舞伎』(服部幸雄/文 一ノ関圭/絵 岩波書店発行)です。
「絵本」といえども侮ってはいけません。
すみずみまで考証されて描かれた魅力的な絵と詳細な解説から構成されており、歌舞伎のことをよーくご存知の方から初心者まで幅広く楽しめる1冊になっています。
電気のない時代の提灯による照明や人力による舞台仕掛けの数々。大勢の裏方さんがいて、大勢のお客さんも一緒になってつくりあげられる舞台空間。知っていたつもりの事柄も、「絵本」という形で提示されることではじめて実感できたり、印象が変わったりします。
常設展示室の模型「中村座」と併せてご覧いただければ面白さも倍増することでしょう。
図書室でちょっと予習をしてから展示室へ繰り出せば、「中村座」から賑やかなお囃子や江戸の人々の歓声が聞こえてくるかもしれませんよ。
最後に、この絵本、すべての絵柄の中に鶴屋南北の弟子の「千松」という男の子がかくれています。ぜひ「千松さがし」にも挑戦してみてください。
1号 2003/5/16 (江戸東京博物館ニューズレター 19号)
<復元・江戸情報地図>
今これを書いている時点で、巷で話題に上っているのが「六本木ヒルズ」のネタ。江戸開府から400周年の東京に、また新しい名所のオープンです−−。
400周年にあわせて、今年一年間、当館でいくつかの企画展を開催する(している)のはご存知の通りです。
この冬の「大江戸八百八町展」もそのひとつでしたが−−この企画展から、企画展示室入口付近の床に設置している「ある江戸図」があります。なかなか好評で、中にははいつくばるように熱心にみている方もあります。これの元になっている本が図書室でみられるというので、図書室に来られる方も増えました。
この本、『復元・江戸情報地図』(児玉幸多監修・吉原健一郎ほか編・朝日新聞社)といいます。
どのような内容かというと、薄線の現代地図の上に重ねあわせて江戸図があらわされているというもので、現在の「この場所」が江戸時代にはどうだったか、何にあたっていたか、といったことがエリア毎にわかるようになっています。
現在のランドマークや自分の住んでいるところを確認したりして、みなさん興味は尽きないようです。
さて、「六本木ヒルズ」に戻って。
この場所をこの本で調べてみると、江戸時代にはまるまる長門府中藩(長府藩)毛利家屋敷だったようです。手元にある「六本木ヒルズ」のガイドをみると・・・なるほどそれでというか、中に「毛利庭園」という施設があります(のこされています)。
とはいえ、この『復元・江戸情報地図』、発行(初版)が1994年で、当然のことながら「六本木ヒルズ」という名前は載っていません。
何でも版元絶版、ゆえに改版予定はないとか。CD-ROM版の『江戸東京重ね地図』が2001年に出てはいるんですが、「やはりページをめくる本じゃないとどうも」などと思うのは
私だけでしょうか(と、これを偶然版元さんが読んでくれて、改版へと翻ってくれないか・・・)。
もっとも、流行ものに即とびつくという性質でない私は、毛利家屋敷跡いや「六本木ヒルズ」にいつ足を運ぶことになるのかわかりませんが。